1はこちら→命の選択のためにやったことー障害者の母になる覚悟はあるか1
2はこちら→命の選択のためにやったことー障害者の母になる覚悟はあるか2
私が"パンドラの箱"と向き合うことになったのは、妊娠を継続した場合の"5"に関してです。
5 運良く出産できたとしても、運良く呼吸できたとしても、重度の腎不全、その他多くの障害を抱え、長くは生きられないかもしれない。
障害のある子供を保育する生活とはどんな生活なのか。
これを私は知っています。
ー医学的な介護
ー社会生活を送る上での社会との摩擦(時にいじめや差別)
ー知的障害がある場合、本人とのコミュニケーションが上手くいかない時の介護者の無力感
ー兄弟に多大な負担
医学的な介護については子供の頃から姉の介護に参加していたので、慣れています。なので、あまりハードルを感じませんでした。いじめや差別も経験しました。
私が姉と過ごす中で辛かったのは残りの二つの部分です。
例えば姉の場合、てんかん発作の一つに呼吸不全があります。脳の誤作動で突然呼吸が止まるのです。寝ていても起きていても、どんな時に起きるかわかりません。私が小学生になる頃には姉妹で一つの部屋だったのですが、夜寝ている時に、突然呼吸が止まり、うっうっと痙攣のような状態になると、私は飛び起きて、「息をするんだよ!息!吸って吐いて、スーハー、スーハー!」と声をかけます。小学生には責任の重すぎる仕事です。(なぜ親とでなく私と相部屋だったのだろう、と今これを書いていて思いました。)
姉のために必要な介助でも、彼女にとってそれが不快であれば、情動発作で泣きわめき、暴れまわります。殴られたり噛まれたりすることも。生まれた時から介護、介助することが当然の環境にいると、磨耗して介護疲れになるのではなく、自我をうまく育てることができず、自分の人生を生きることが難しくなります。
何がおかしくて何が普通なのかわからないのです。介護疲れにはレスパイトという方法がありますが、"自分"がなければ疲れたと感じることもありません。東京の大学に進学し、一度たりとも帰省しなかった3年間に私は自分を取り戻すことができました。そんな経験を私の長男には絶対にさせたくなかったのです。
また、腎臓は移植できる臓器です。私たち親の年齢が高齢化して、次男に腎臓を提供できなくなった時、献腎移植の順番が回ってこなければ、長男が次男に腎臓を上げなくてはならない、というプレッシャーを感じるかもしれない、と思うと、そのことでも身が切られるような思いがしました。
母は私に兄弟児のケアを全くできなかったことを、強く後悔しており、次男を堕胎するよう、言ったのです。
産みたい、一緒に生きたい。
けれど親のエゴを長男にも押しつけることになりはしないか。
6日間、ベッドにうずくまってお腹に一番負担をかけないとされるシムスの体位を取りながら延々と同じことを考えていました。まさにパンドラの箱です。
答えは思わぬところからやってきました。
夫です。
「Annには誰もおらんかったかもしれないけど、長男にはAnnがいるし、俺もいるし、大丈夫や、みんないるから大丈夫や」
(私たち夫婦は東京在住の関西人です。夫婦で話すときは関西弁です。)
長男を妊娠した時にも、満たされなかった子供時代がフラッシュバックし、子供を愛せなかったらどうしようという強い不安に苛まれました。その時も、
「もしもAnnが子供を愛せなかったら、子供を置いて離婚してええよ、俺が育てるから大丈夫。」という言葉で踏ん切りがつきました、そうだ、一人じゃない、もし私が暴走しても止めてくれる人がいる。そう思えました。
そうです、私は障害者の家族であることをすでに知っています。
医療的ケアも慣れています。社会摩擦があることも知っています。
むしろ、障害を抱えるかもしれない赤ちゃんを迎えるにはポテンシャルのある母親じゃないか。何が怖かったのか。私も含め、家族の誰かが、とりわけ長男が独りぼっちになるのが怖かったのです。
パンドラの箱の底に残ったのは、一人じゃない、という希望でした。
にほんブログ村
にほんブログ村

子供・赤ちゃんランキング
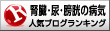
腎臓・尿・膀胱ランキング






0 件のコメント:
コメントを投稿